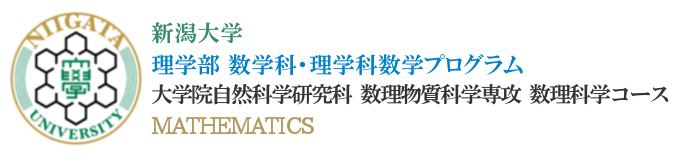数学プログラムの特徴
- これまでの「数学科」と同じように数学を専門的に学ぶことができます。
- 数学の理論だけでなく、数学を用いて問題解決を目指す「応用数学」にも力を入れています。
- 大学院でさらに数学を学ぶことも可能です。
- 中学校・高等学校の教員免許状(数学)が取得可能です。
- 卒業後は様々な職種に就いています。数学科からは大学院進学だけでなく、教員・一般企業への就職実績が多数あります。
平成27年度実績:新潟大学大学院、中学校教員、高校教員、公務員、 (株)エヌ・シー・エス、(株)第四銀行、キヤノンイメージングシステムズ(株)、(株)ソリマチ技研、東京コンピューターサービス、スタディ・フィールド、ドメーム・ショオ、福島銀行、丸三証券(株)、京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)宮城県農協情報センター、東日本旅客鉄道(株)、(株)ブレイブソフト、国立病院機構(関東信越)
数学科から数学プログラムへの主な変更点
- 入学時にプログラムを決める必要はありません。
- プログラムは2年生前半終了までに希望調査を行い、2年生後半開始時に配属されます。
- 数学プログラムの上限目安は「50人」です。これまでの数学科定員は35人でしたので、学生の希望が生かされるように上限目安は設定されています。
- 数学プログラムには「専門力」と「総合力」があり、自分でどちらかを選べます。
(1) 「専門力プログラム」では数学そのものを学び、深く理解することを目指します。
(2) 「総合力プログラム」では数学を中心に幅広い科学分野の基礎知識を獲得することができます。 - 数学プログラムでは、教員免許状(情報)を取得することができません。
- 前期日程出願者で、数学プログラムへの志望が明確な者は、出願時に「フロンティア・スタディ・プロジェクト」に申請することにより、1年次から数学プログラムを選ぶことができます。【入試成績上位者の中から理学部全体で30人程度】
一般入試(前期日程・後期日程)
- 理学部理学科の前期日程の選抜方法、概ねの募集人員、個別学力検査の配点は以下の通りです。
選抜方法A(52人): 数学(400点)、理科(300点)、外国語(100点) 選抜方法B(61人): 数学、理科から2科目(300点×2)、外国語(200点) 選抜方法C(20人): 数学、理科から2科目(300点×2)、面接(100点)
選抜方法Cにおいてはフィールドワークや野外を対象とする自然科学分野に対する意欲と適正を面接によってはかります。 - 理学部理学科の後期日程の個別学力検査では、面接を実施します。概ねの募集人員は32人です。